犯罪被害者支援
デジタルライブラリーDigital Library for Victim Support
study学ぶ
result「犯罪被害者支援」一覧
-
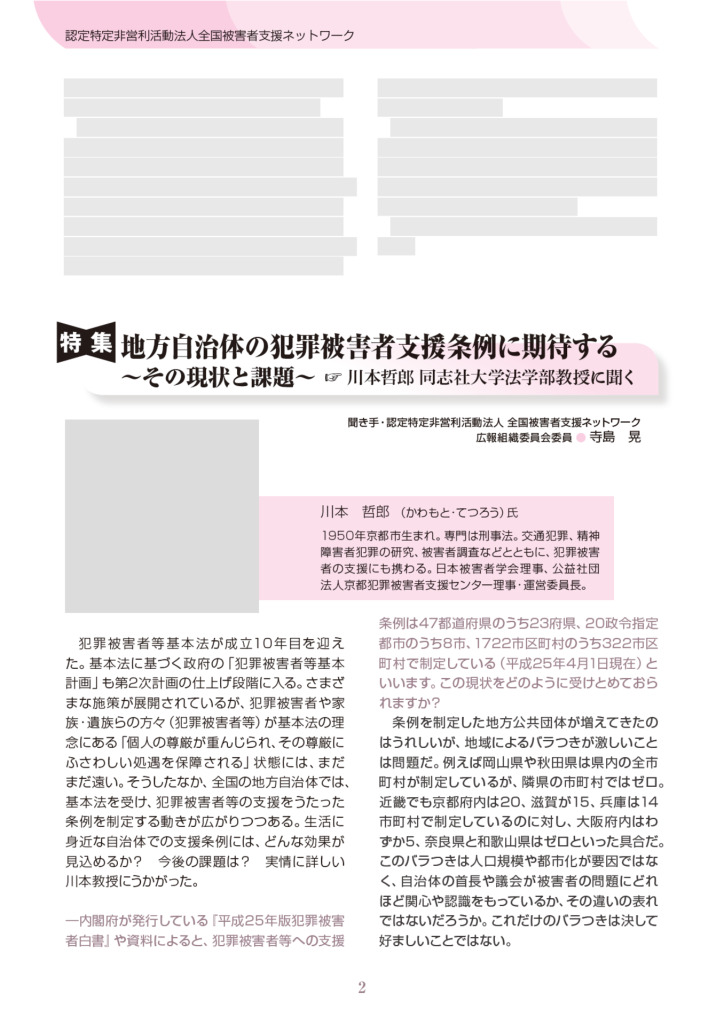 被害者支援ニュース地方自治体の犯罪被害者支援条例に期待する~その現状と課題~
被害者支援ニュース地方自治体の犯罪被害者支援条例に期待する~その現状と課題~犯罪被害者や家族・遺族らの方々(犯罪被害者等)が基本法の理念にある「個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される」状態には、まだまだ遠い。そうしたなか、全国の地方自治体では、基本法を受け、犯罪被害者等の支援をうたった条例を制定する動きが広がりつつある。生活に身近な自治体での支援条例には、どんな効果が見込めるか? 今後の課題は?
条例犯罪被害者支援自治体関係機関連携 -
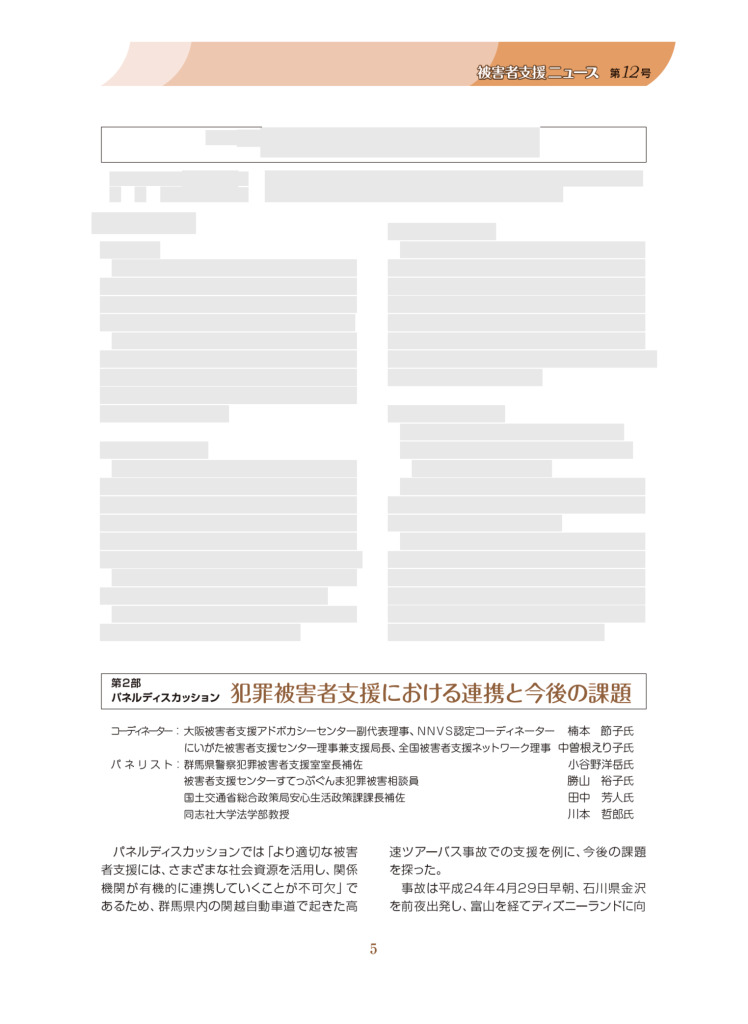 被害者支援ニュース犯罪被害者支援における連携と今後の課題
被害者支援ニュース犯罪被害者支援における連携と今後の課題「より適切な被害者支援には、さまざまな社会資源を活用し、関係機関が有機的に連携していくことが不可欠」であるため、群馬県内の関越自動車道で起きた高速ツアーバス事故での支援を例に、今後の課題を探った。
犯罪被害者支援関係機関連携 -
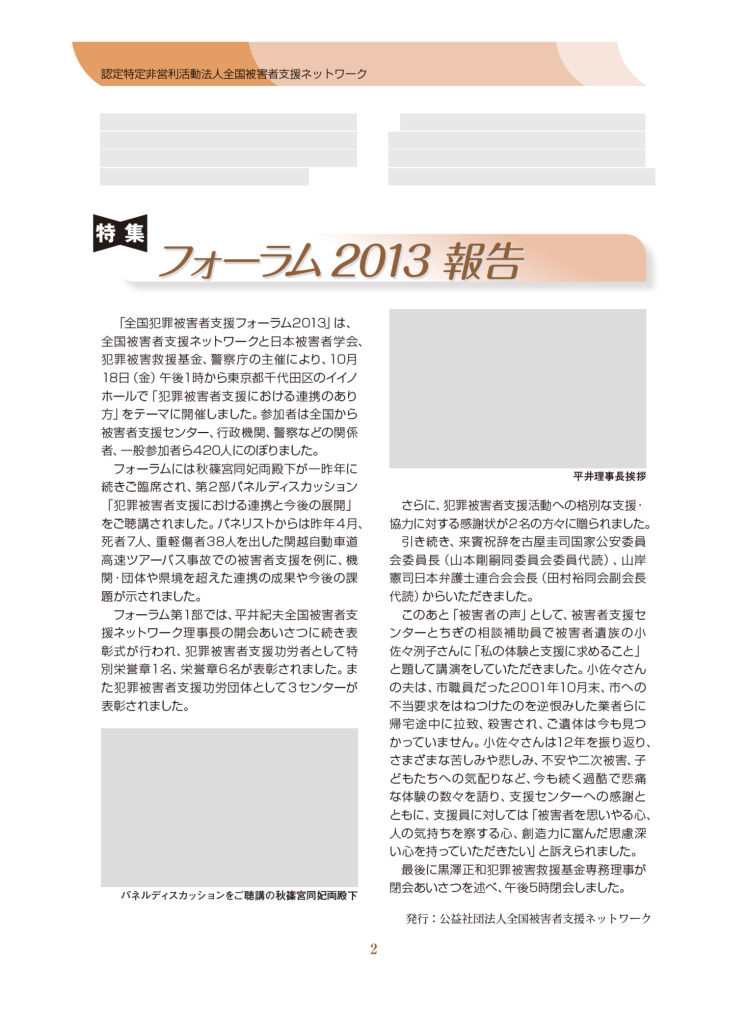 被害者支援ニュースフォーラム2013 報告
被害者支援ニュースフォーラム2013 報告「犯罪被害者支援における連携のあり方」をテーマに開催しました。参加者は全国から被害者支援センター、行政機関、警察などの関係者、一般参加者ら420人にのぼりました。フォーラムには秋篠宮同妃両殿下が一昨年に続きご臨席され、第2部パネルディスカッション「犯罪被害者支援における連携と今後の展開」をご聴講されました。
広報啓発民間被害者支援団体犯罪被害者支援 -
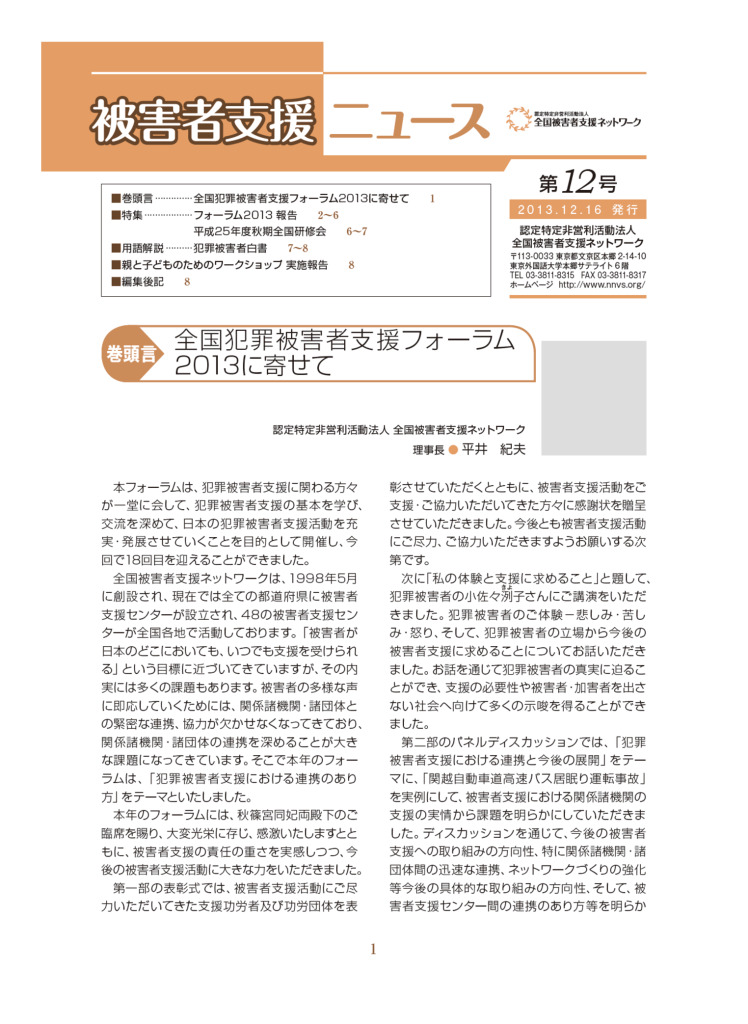 被害者支援ニュース全国犯罪被害者支援フォーラム2013に寄せて
被害者支援ニュース全国犯罪被害者支援フォーラム2013に寄せて被害者の多様な声に即応していくためには、関係諸機関・諸団体との緊密な連携、協力が欠かせなくなってきており、関係諸機関・諸団体の連携を深めることが大きな課題になってきています。そこで本年のフォーラムは、「犯罪被害者支援における連携のあり方」をテーマといたしました。
広報啓発民間被害者支援団体犯罪被害者支援 -
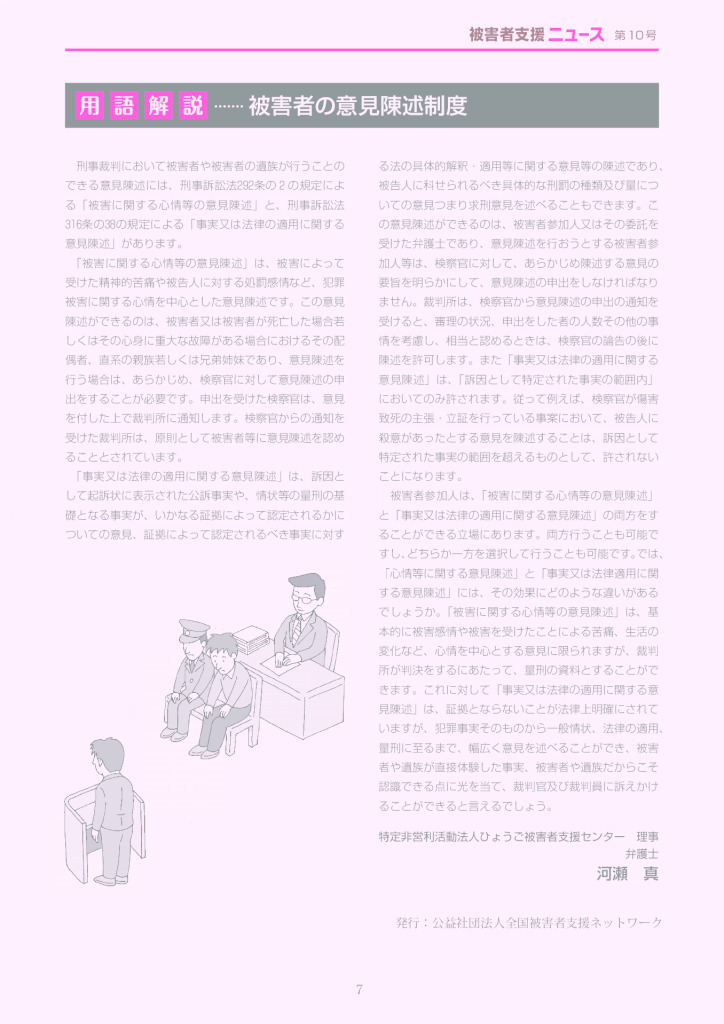 被害者支援ニュース被害者の意見陳述制度
被害者支援ニュース被害者の意見陳述制度刑事裁判において被害者や被害者の遺族が行うことのできる意見陳述には、刑事訴訟法292条の2 の規定による「被害に関する心情等の意見陳述」と、刑事訴訟法316条の38の規定による「事実又は法律の適用に関する意見陳述」があります。
犯罪被害者支援