犯罪被害者支援
デジタルライブラリーDigital Library for Victim Support
study学ぶ
result「犯罪被害者支援」一覧
-
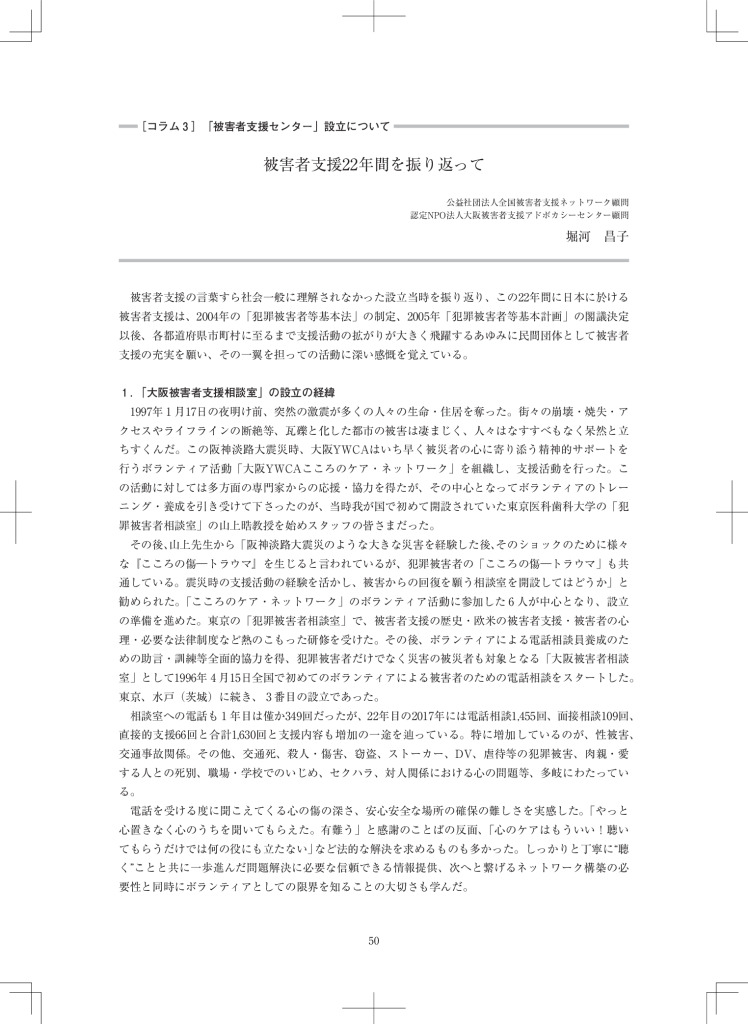 民間団体による犯罪被害者支援の歴史と展望─全国被害者支援ネットワーク 創立20周年記念誌─被害者支援22年間を振り返って
民間団体による犯罪被害者支援の歴史と展望─全国被害者支援ネットワーク 創立20周年記念誌─被害者支援22年間を振り返って被害者支援の言葉すら社会一般に理解されなかった設立当時を振り返り、この22年間に日本に於ける被害者支援は、2004年の「犯罪被害者等基本法」の制定、2005年「犯罪被害者等基本計画」の閣議決定以後、各都道府県市町村に至るまで支援活動の拡がりが大きく飛躍するあゆみに民間団体として被害者支援の充実を願い、その一翼を担っての活動に深い感慨を覚えている。
民間被害者支援団体犯罪被害者支援被害者支援センター -
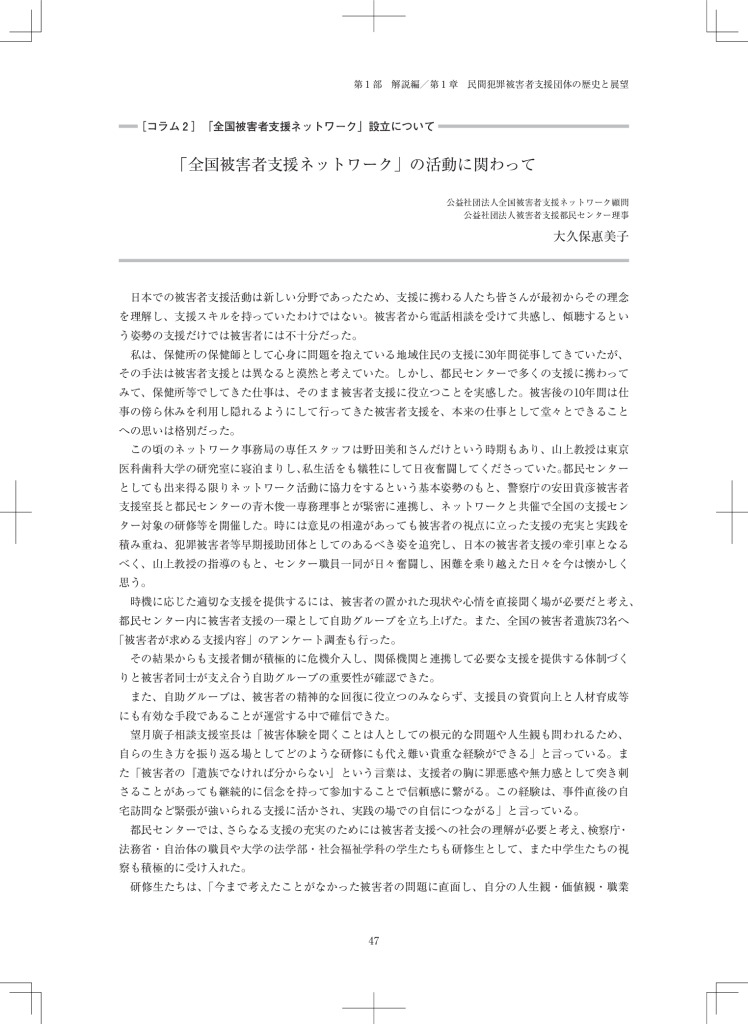 民間団体による犯罪被害者支援の歴史と展望─全国被害者支援ネットワーク 創立20周年記念誌─「全国被害者支援ネットワーク」の活動に関わって
民間団体による犯罪被害者支援の歴史と展望─全国被害者支援ネットワーク 創立20周年記念誌─「全国被害者支援ネットワーク」の活動に関わって日本での被害者支援活動は新しい分野であったため、支援に携わる人たち皆さんが最初からその理念を理解し、支援スキルを持っていたわけではない。被害者から電話相談を受けて共感し、傾聴するという姿勢の支援だけでは被害者には不十分だった。
民間被害者支援団体犯罪被害者支援被害当事者被害者支援センター -
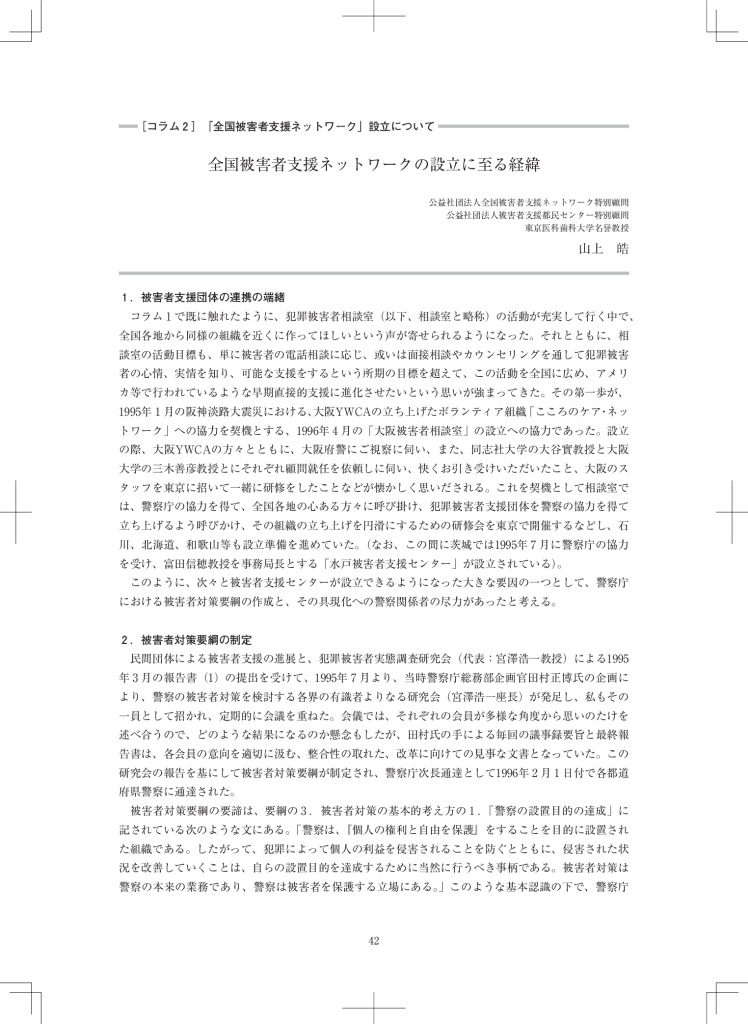 民間団体による犯罪被害者支援の歴史と展望─全国被害者支援ネットワーク 創立20周年記念誌─全国被害者支援ネットワークの設立に至る経緯
民間団体による犯罪被害者支援の歴史と展望─全国被害者支援ネットワーク 創立20周年記念誌─全国被害者支援ネットワークの設立に至る経緯犯罪被害者相談室(以下、相談室と略称)の活動が充実して行く中で、全国各地から同様の組織を近くに作ってほしいという声が寄せられるようになった。それとともに、相談室の活動目標も、単に被害者の電話相談に応じ、或いは面接相談やカウンセリングを通して犯罪被害者の心情、実情を知り、可能な支援をするという所期の目標を超えて、この活動を全国に広め、アメリカ等で行われているような早期直接的支援に進化させたいという思いが強まってきた。
民間被害者支援団体犯罪被害者支援被害者支援センター -
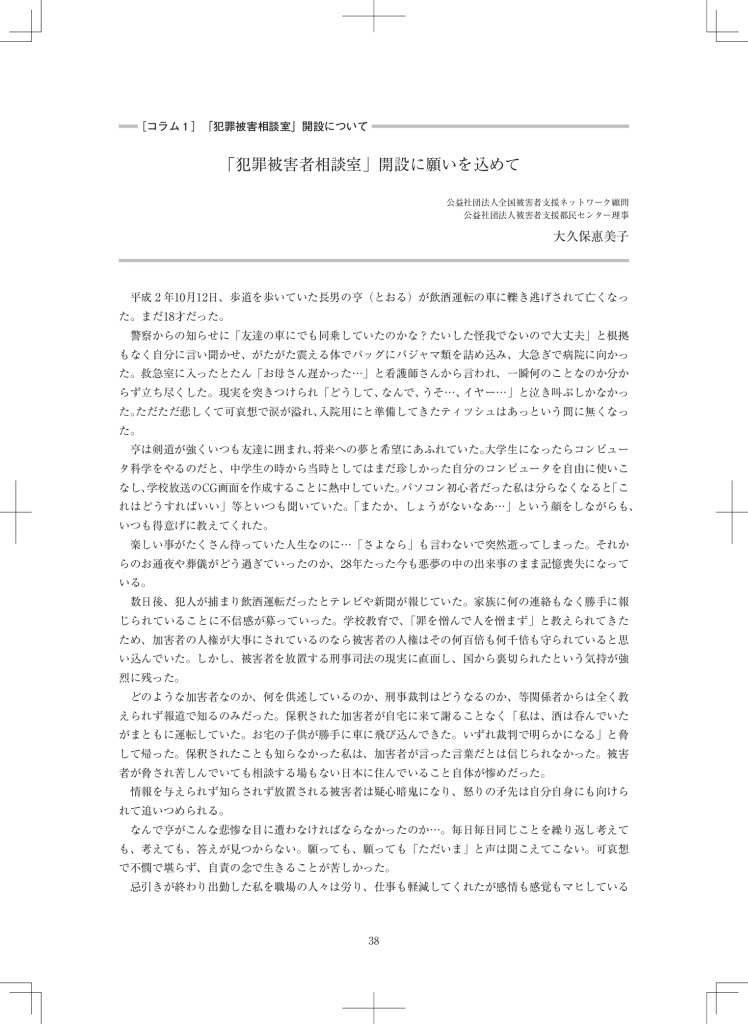 民間団体による犯罪被害者支援の歴史と展望─全国被害者支援ネットワーク 創立20周年記念誌─「犯罪被害者相談室」開設に願いを込めて
民間団体による犯罪被害者支援の歴史と展望─全国被害者支援ネットワーク 創立20周年記念誌─「犯罪被害者相談室」開設に願いを込めて歩道を歩いていた長男が飲酒運転の車に轢き逃げされて亡くなった。まだ18才だった。 警察からの知らせに「友達の車にでも同乗していたのかな?たいした怪我でないので大丈夫」と根拠もなく自分に言い聞かせ、がたがた震える体でバッグにパジャマ類を詰め込み、大急ぎで病院に向かった。救急室に入ったとたん「お母さん遅かった…」と看護師さんから言われ、一瞬何のことなのか分からず立ち尽くした。現実を突きつけられ「どうして、なんで、うそ…、イヤー…」と泣き叫ぶしかなかった。ただただ悲しくて可哀想で涙が溢れ、入院用にと準備してきたティツシュはあっという間に無くなった
民間被害者支援団体犯罪被害者支援被害当事者被害者支援センター -
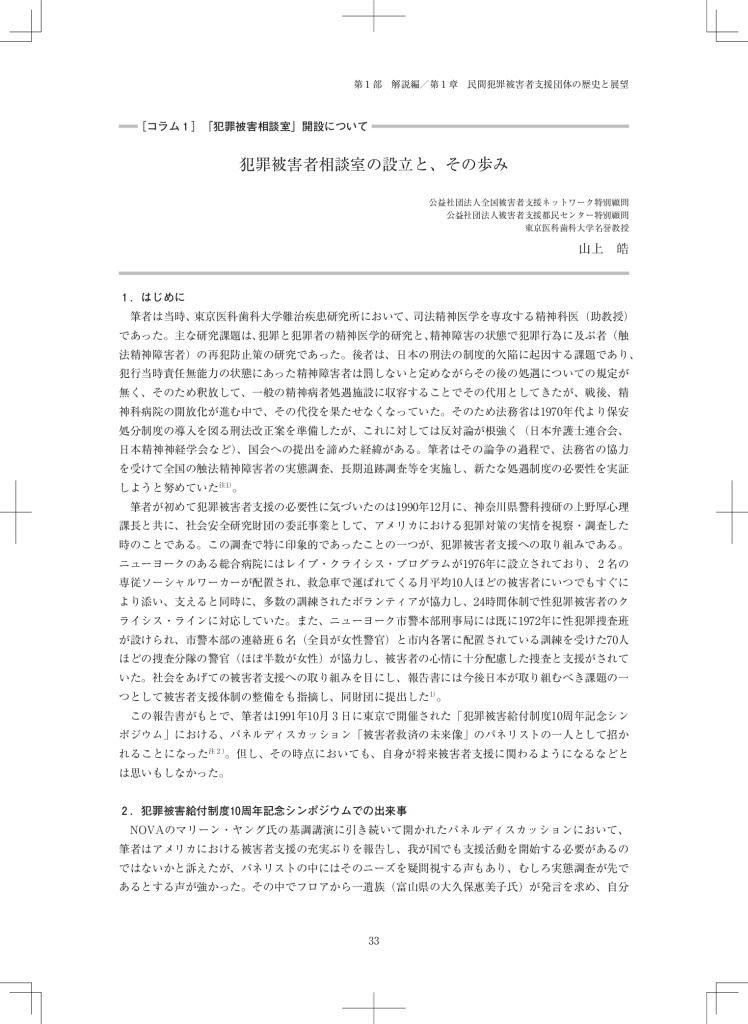 民間団体による犯罪被害者支援の歴史と展望─全国被害者支援ネットワーク 創立20周年記念誌─犯罪被害者相談室の設立と、その歩み
民間団体による犯罪被害者支援の歴史と展望─全国被害者支援ネットワーク 創立20周年記念誌─犯罪被害者相談室の設立と、その歩み筆者は当時、東京医科歯科大学難治疾患研究所において、司法精神医学を専攻する精神科医(助教授)であった。主な研究課題は、犯罪と犯罪者の精神医学的研究と、精神障害の状態で犯罪行為に及ぶ者(触法精神障害者)の再犯防止策の研究であった。後者は、日本の刑法の制度的欠陥に起因する課題であり、犯行当時責任無能力の状態にあった精神障害者は罰しないと定めながらその後の処遇についての規定が無く、そのため釈放して、一般の精神病者処遇施設に収容することでその代用としてきたが、戦後、精神科病院の開放化が進む中で、その代役を果たせなくなっていた。
民間被害者支援団体犯罪被害者支援