犯罪被害者支援
デジタルライブラリーDigital Library for Victim Support
study学ぶ
result「被害者支援ニュース」一覧
-
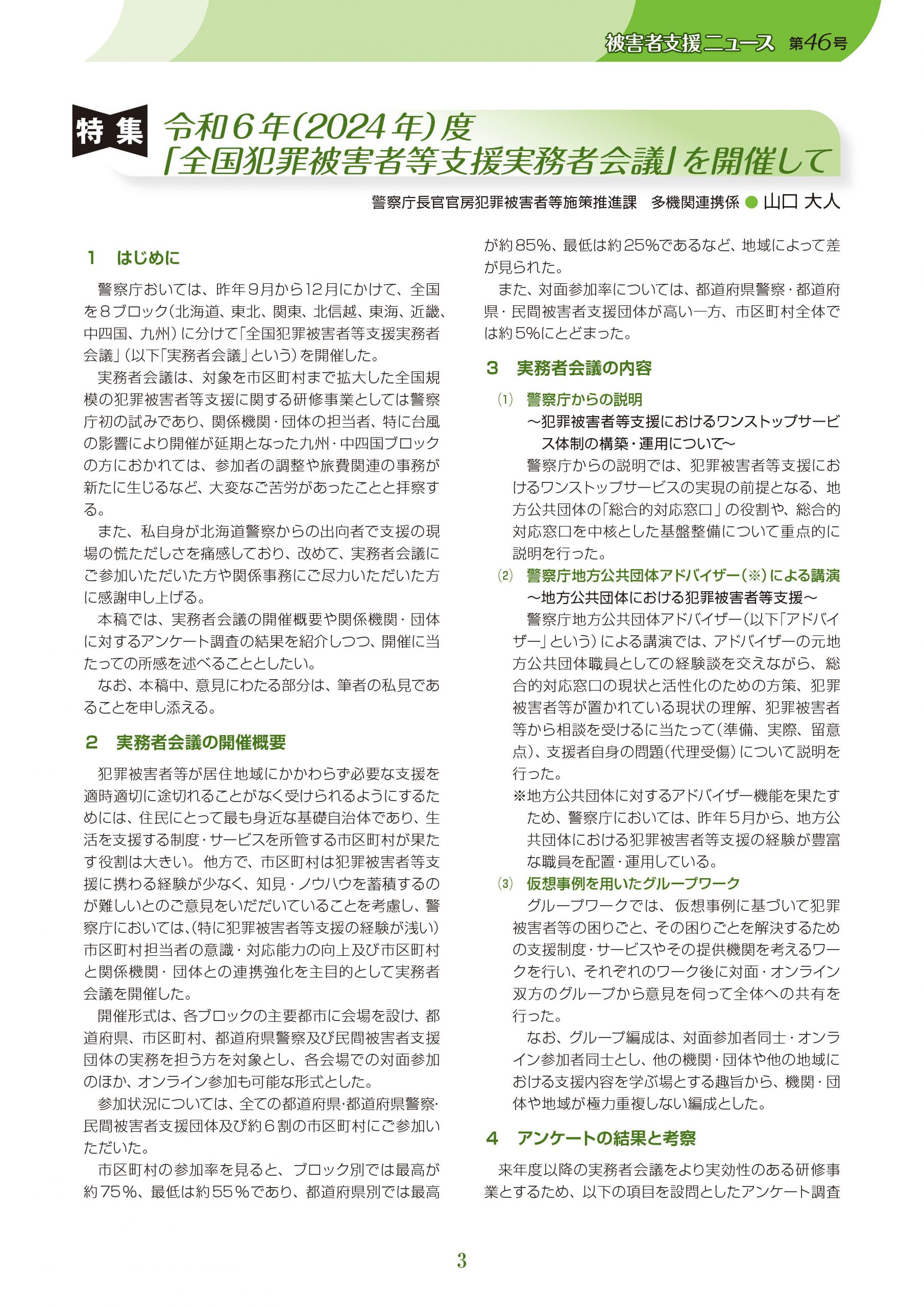 被害者支援ニュース特 集 令和6年(2024年)度「全国犯罪被害者等支援実務者会議」を開催して
被害者支援ニュース特 集 令和6年(2024年)度「全国犯罪被害者等支援実務者会議」を開催して警察庁おいては、昨年9月から12 月にかけて、全国を8 ブロック(北海道、東北、関東、北信越、東海、近畿、中四国、九州)に分けて「全国犯罪被害者等支援実務者会議」(以下「実務者会議」という)を開催した。実務者会議は、対象を市区町村まで拡大した全国規模の犯罪被害者等支援に関する研修事業としては警察庁初の試みであり、関係機関・団体の担当者、特に台風の影響により開催が延期となった九州・中四国ブロックの方におかれては、参加者の調整や旅費関連の事務が新たに生じるなど、大変なご苦労があったことと拝察する。また、私自身が北海道警察からの出向者で支援の現場の慌ただしさを痛感しており、改めて、実務者会議にご参加いただいた方や関係事務にご尽力いただいた方に感謝申し上げる。本稿では、実務者会議の開催概要や関係機関・団体に対するアンケート調査の結果を紹介しつつ、開催に当たっての所感を述べることとしたい。
支援コーディネーター支援実務者会議犯罪被害者支援自治体被害者支援センター途切れない支援 -
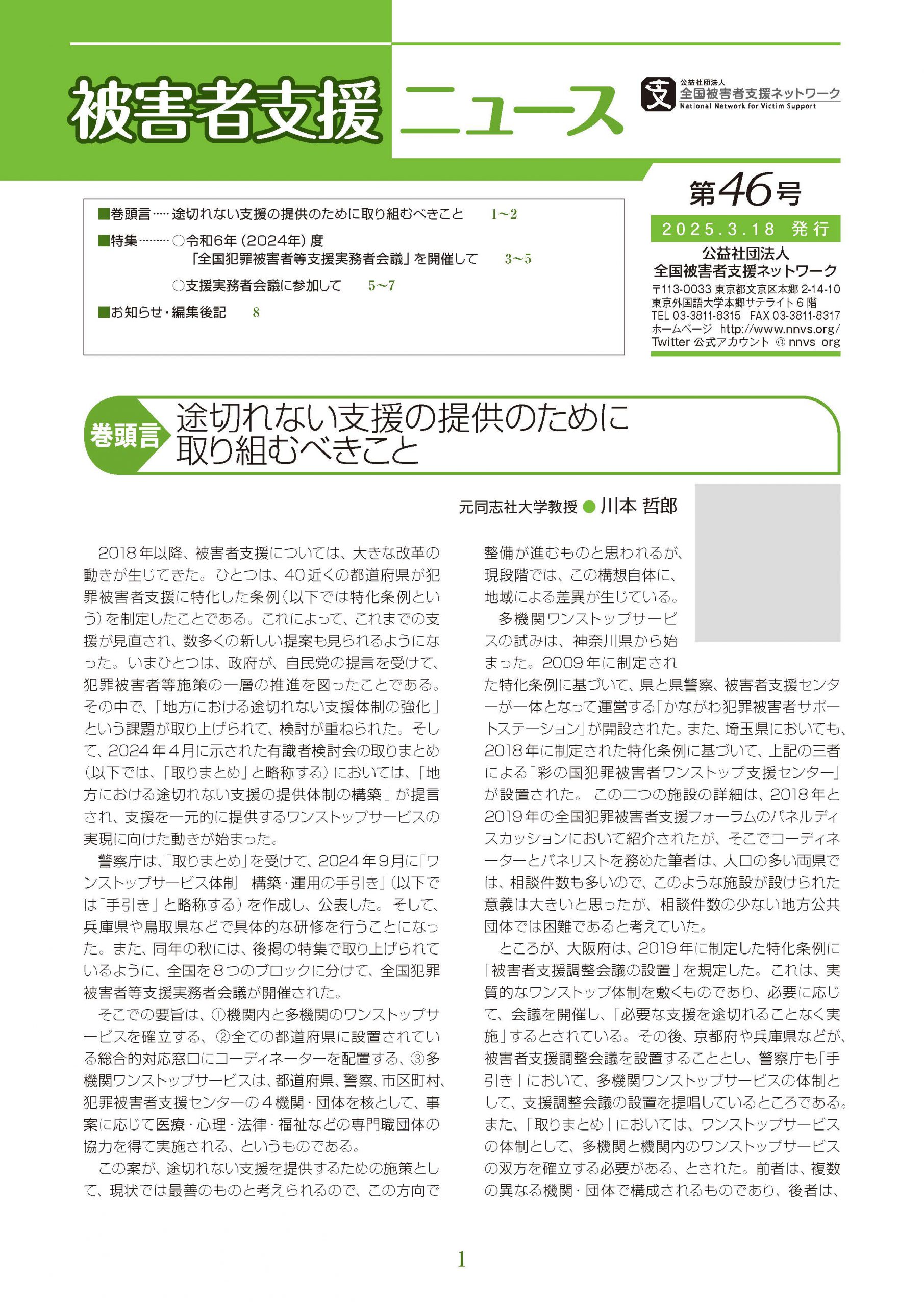 被害者支援ニュース巻頭言 途切れない支援の提供のために取り組むべきこと
被害者支援ニュース巻頭言 途切れない支援の提供のために取り組むべきこと2018 年以降、被害者支援については、大きな改革の動きが生じてきた。ひとつは、40 近くの都道府県が犯罪被害者支援に特化した条例(以下では特化条例という)を制定したことである。これによって、これまでの支援が見直され、数多くの新しい提案も見られるようになった。いまひとつは、政府が、自民党の提言を受けて、犯罪被害者等施策の一層の推進を図ったことである。その中で、「地方における途切れない支援体制の強化」という課題が取り上げられて、検討が重ねられた。そして、2024 年4月に示された有識者検討会の取りまとめ(以下では、「取りまとめ」と略称する)においては、「地方における途切れない支援の提供体制の構築」が提言され、支援を一元的に提供するワンストップサービスの実現に向けた動きが始まった。警察庁は、「取りまとめ」を受けて、2024 年9月に「ワンストップサービス体制 構築・運用の手引き」(以下では「手引き」と略称する)を作成し、公表した。
支援コーディネーター支援実務者会議犯罪被害者支援自治体被害者支援センター途切れない支援 -
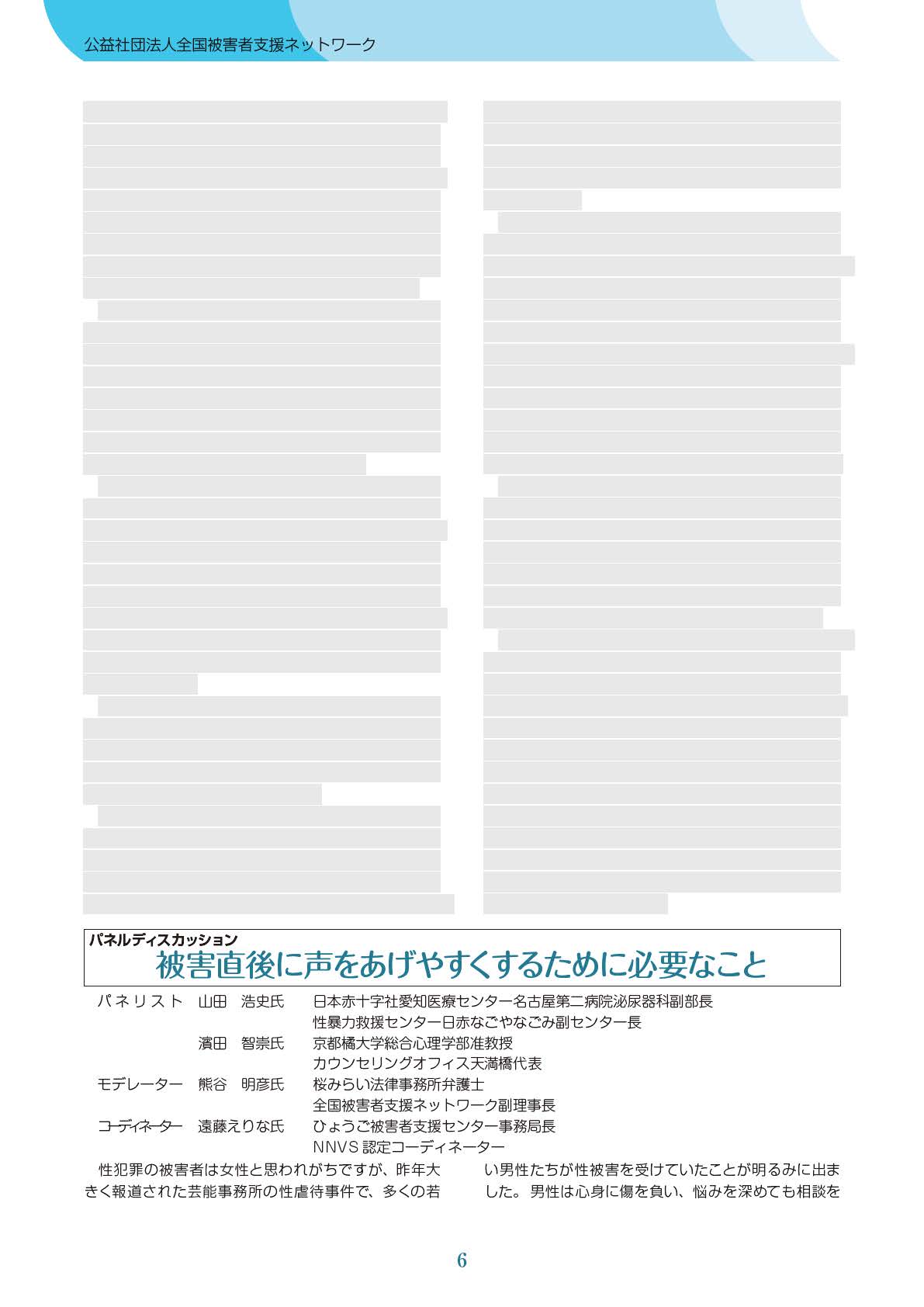 被害者支援ニュースパネルディスカッション 被害直後に声をあげやすくするために必要なこと
被害者支援ニュースパネルディスカッション 被害直後に声をあげやすくするために必要なこと性犯罪の被害者は女性と思われがちですが、昨年大きく報道された芸能事務所の性虐待事件で、多くの若い男性たちが性被害を受けていたことが明るみに出ました。男性は心身に傷を負い、悩みを深めても相談をためらう傾向があるといいます。パネルディスカッションでは、男性被害の実態を踏まえて、男性が声を上げやすくする手立てや、これまで経験の少なかった支援のこれからを考えました。
境界線心理的支援性暴力とは性暴力被害者性犯罪とは性犯罪被害者支援支援体制民間被害者支援団体男児男性 -
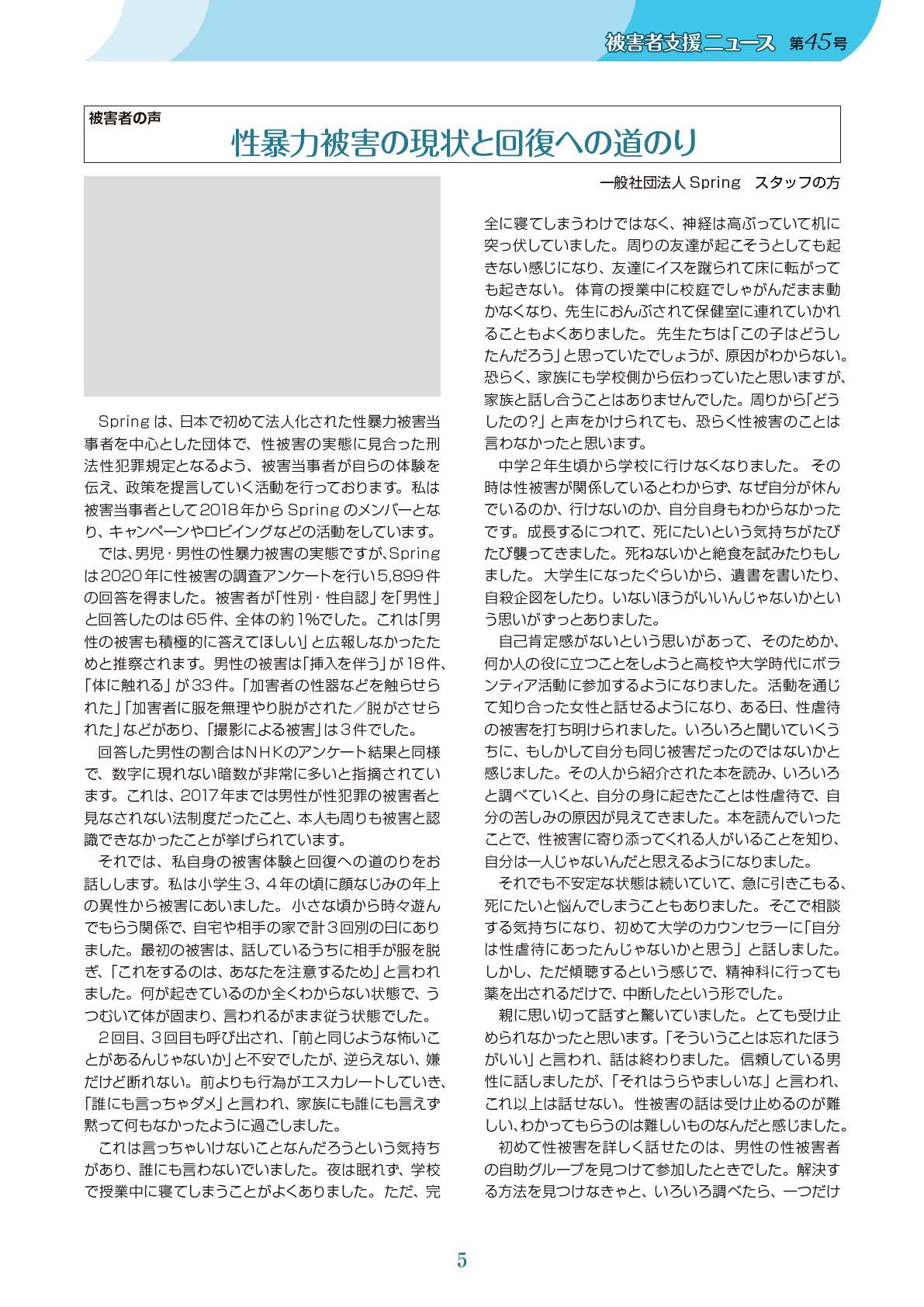 被害者支援ニュース被害者の声 性暴力被害の現状と回復への道のり
被害者支援ニュース被害者の声 性暴力被害の現状と回復への道のりSpring は、日本で初めて法人化された性暴力被害当事者を中心とした団体で、性被害の実態に見合った刑法性犯罪規定となるよう、被害当事者が自らの体験を伝え、政策を提言していく活動を行っております。私は被害当事者として2018 年からSpring のメンバーとなり、キャンペーンやロビイングなどの活動をしています。
性暴力とは性暴力被害者性犯罪とは性犯罪被害者男児男性 -
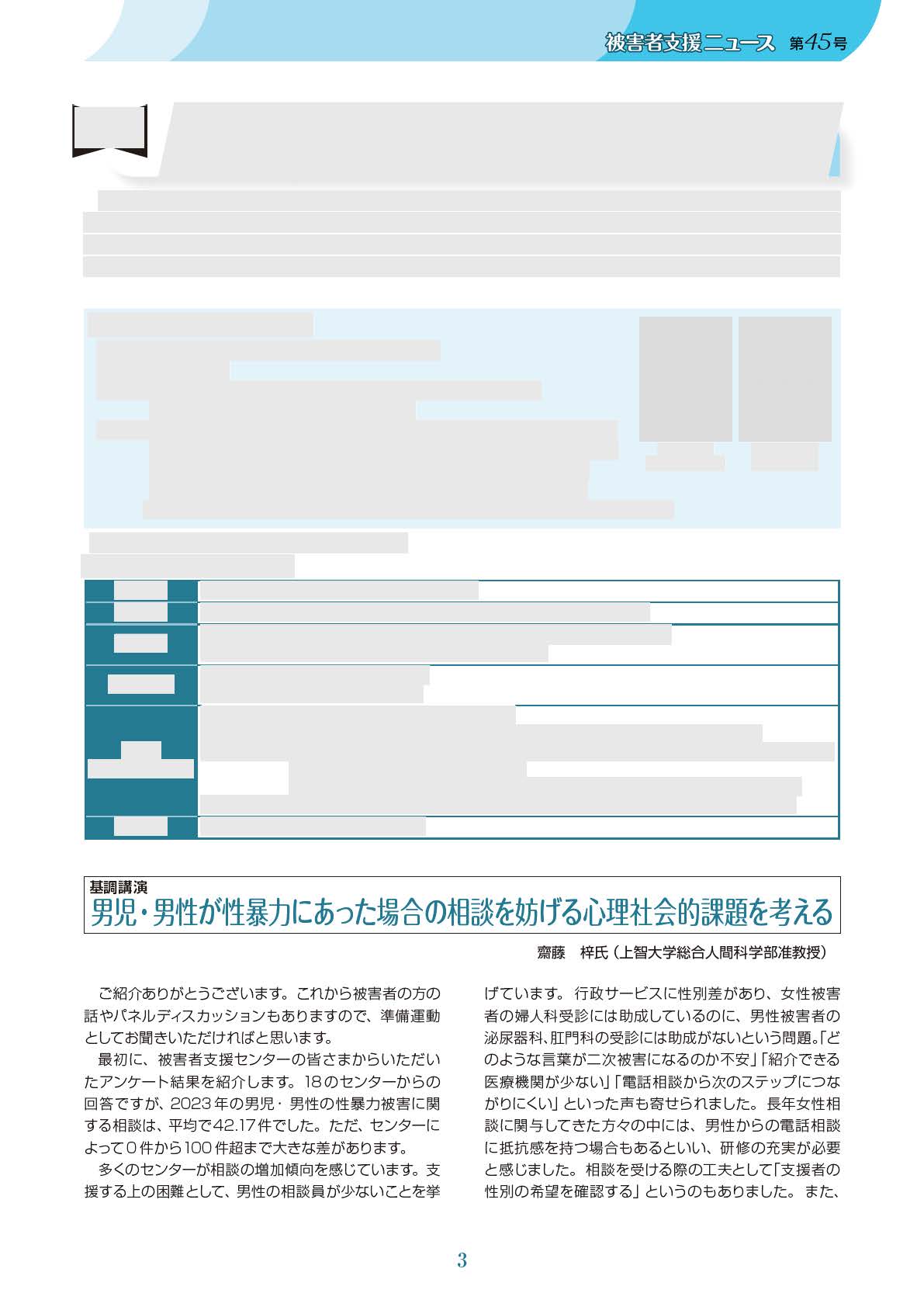 被害者支援ニュース“基調講演 男児・男性が性暴力にあった場合の相談を妨げる心理社会的課題を考える “
被害者支援ニュース“基調講演 男児・男性が性暴力にあった場合の相談を妨げる心理社会的課題を考える “「性暴力はなぜ『暴力』なのか」について話していきます。私は心理職として心理の境界線という概念で考えます。境界線は、自分が安心と感じる領域を守る線です。例えば「シャープペンシルを貸して」と言って、「いいよ」と言われて借りるのが普通です。貸すか貸さないかは持ち主が決めていい。性にも境界線があって、いつ、誰と、どんな性的行為をするか、自分で決めていいはず。自分の意志や感情がないがしろにされると、安心や安全が脅かされるということです。子どもの頃から性の境界線が侵害されていると感じています。スカートめくりやズボンおろしを多くの人が覚えています。それで傷ついても、「気にしないで」「いたずらだよ」と言われる。そうなると自分の体は大事にされていない、体の決定権は自分にはないと感じ、自分の性的な境界線を決めるのが難しくなっていく。そういう社会ではないかと。
境界線心理的支援性暴力とは性暴力被害者性犯罪とは性犯罪被害者支援支援体制民間被害者支援団体男児男性